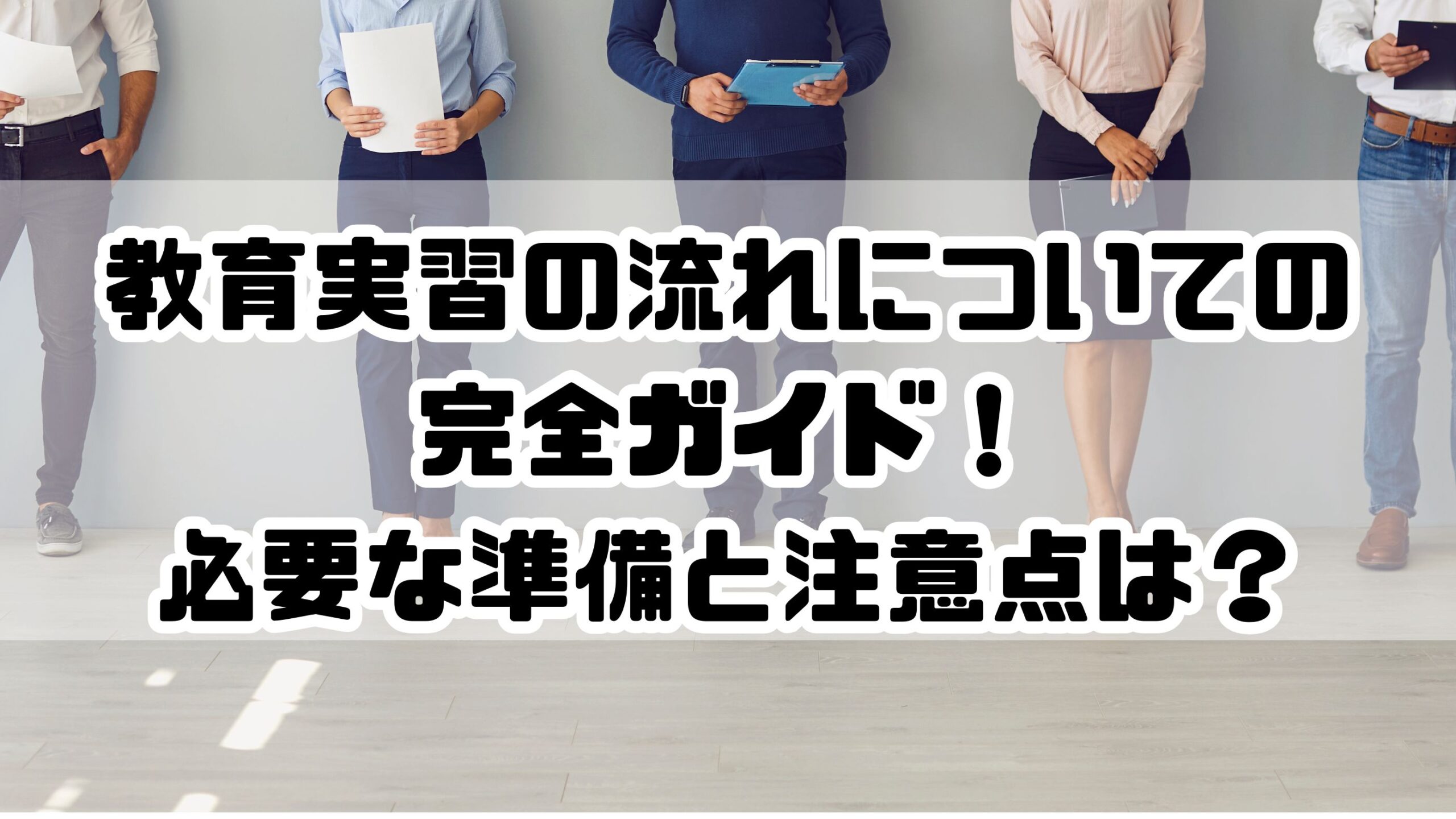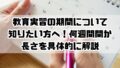教育実習は、将来教師を目指す人にとって欠かせない大切な経験です。
でも、はじめてのことばかりで不安になりますよね。
この記事では、教育実習の流れをわかりやすく、そして実体験を交えながら丁寧に解説します。
教育実習の流れとは?

教育実習の目的と重要性
教育実習は、将来教師になるための大切な一歩です。
教える技術や授業の進め方を学ぶのはもちろん、学校という現場でしか味わえない「生の教育」を体験するチャンスです。
子どもたちと接することで、机上では得られない学びをたくさん得られます。
私が実習中に驚いたのは、授業だけでなく掃除や行事など、学校生活のすべてが教育だということでした。
とある日、生徒に名前を呼ばれて「先生!」と笑顔で話しかけられたとき、心から「教師って素晴らしいな」と思えました。
このような経験が、教職に就く覚悟を強くしてくれたのです。
教育実習の基本的な流れ
教育実習は、いくつかの段階に分かれています。
準備から終了までの一連の流れを、下の表にまとめてみました。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 事前準備 | 実習先との打ち合わせや教材の準備、自己紹介資料の作成 |
| 2. 実習スタート | 初日の全体会・職員室への挨拶・校内案内 |
| 3. 授業見学 | 先輩教師の授業を観察し、記録をとる |
| 4. 授業実践 | 指導案に沿って自分で授業を行う |
| 5. 振り返り | 教師や自分による授業の評価・改善点の確認 |
| 6. 実習終了 | 感謝の手紙や報告書提出・最終日挨拶 |
このように、段階を追って学びながら実践していく流れです。
日々の記録を丁寧に取り、成長を感じることも大切です。
教育実習での体験について
ある日、私は理科の授業で「酸とアルカリ」の実験をしました。
色が変わるリトマス紙に、子どもたちは興味津々。ところが、予想外に反応がうまく出ず、私は内心とても焦りました。
でも、生徒が「次はどうなるかな?」「もう一回やって!」と声をかけてくれて、私も笑顔を取り戻せました。
このような失敗も、現場ならではの貴重な学びです。
\毎日ポイントがザクザクたまってお得!/ 楽天人気ランキングページはこちら<PR>
教育実習の事前準備
実習先学校との打ち合わせ
教育実習の開始前には、実習先の学校と事前打ち合わせを行います。
日時や服装、授業数など、基本的な情報だけでなく、学校の教育方針や担当教諭の指導スタイルについても確認します。
実際に訪問して校内を案内してもらうことで、実習当日の不安がぐっと減ります。
実習初日にスムーズに動けるよう、持ち物リストを作っておくと安心ですよ。
必要な教材研究と準備
授業で使う教材は、見た目以上に準備が大変です。
教科書だけでなく、補助資料、映像資料、プリントなど多角的に情報を集めておくことが大切です。
授業の流れや、生徒のつまずきやすいポイントも事前に把握しておきましょう。
板書の練習や、声の出し方の練習もしておくと本番で自信が持てます。
履修しておくべき科目
教育実習に進むためには、大学で一定の教職関連科目を履修しておく必要があります。
| 科目 | 内容 |
| 教職論 | 教師の仕事や使命、教育の目的を学ぶ |
| 教育心理学 | 子どもの発達や心の仕組みを学び、理解を深める |
| 教育方法論 | 効果的な教え方、学習指導案の作成方法などを習得する |
| 教育実習事前指導 | 実習に向けて心構えや実践力を高める講義 |
これらの科目を通じて、教育に必要な基礎力を身につけます。
\毎日ポイントがザクザクたまってお得!/ 楽天人気ランキングページはこちら<PR>
教育実習中の授業に関する注意点
授業の進行と指導のポイント
授業を成功させるには、時間配分とわかりやすさのバランスが重要です。
例えば「導入→本題→まとめ」という構成を意識することで、授業がスムーズに進みます。
私は初めて授業をしたとき、内容を詰め込みすぎて後半が駆け足になってしまいました。
それ以来、時計を見ながら「ここで切り上げよう」と意識するようにしています。
クラスメイトとの協力
教育実習には、大学の仲間と一緒に行くことが多くあります。
同じ学年の実習生と情報交換をしたり、授業のリハーサルを見合ったりすることで、多くの気づきが得られます。
互いの成功体験や失敗談を共有すると、安心感が生まれます。
「一人じゃない」という気持ちは、大きな支えになります。
生徒への接し方と配慮
生徒に接する際は、言葉選びや態度に十分気を配りましょう。
注意するときも、責めるのではなく「どうすればよかったと思う?」と問いかける姿勢が大切です。
名前を覚えて呼ぶ、目線を合わせて話すなど、小さなことが信頼関係を築くポイントになります。
\毎日ポイントがザクザクたまってお得!/ 楽天人気ランキングページはこちら<PR>
教育実習のスケジュール管理
週間スケジュールの作成
スケジュールを立てることは、教育実習を乗り切る大きな武器になります。
次のような表で、自分の活動を見える化しておくと安心です。
| 日時 | 内容 |
| 月曜日 | 授業2コマ・指導案提出・放課後反省会 |
| 火曜日 | 教室観察・教材準備・教員との打ち合わせ |
| 水曜日 | 実践授業・フィードバック受領・個人振り返り |
| 木曜日 | 授業実践・教材修正・模擬授業練習 |
| 金曜日 | 授業・お礼の挨拶・週末まとめレポート作成 |
このように事前に計画することで、実習中の負担を軽くできます。
帰宅時間の設定と労働時間
教育実習中は朝が早く、放課後も会議や準備で遅くなりがちです。
睡眠時間を確保し、体調を崩さないようにすることが何よりも大切です。
私は、22時までには帰宅すると決めて、どんなに忙しくても自分のリズムを守るようにしていました。
健康が保てないと、よい授業もできませんからね。
適切な活動の計画
授業の他にも、運動会や文化祭など学校行事の手伝いもあります。
それらをどのようにサポートできるかを考えながら行動することも、教育実習の一環です。
私は合唱練習にピアノ伴奏として参加し、生徒たちと一体感を味わうことができました。
授業以外の活動こそ、生徒と深く関われる貴重な時間です。
\毎日ポイントがザクザクたまってお得!/ 楽天人気ランキングページはこちら<PR>
実習中の観察とフィードバック
授業の観察方法
先輩教師の授業を観察することは、自分の授業力を高めるための近道です。
単に見るのではなく、「なぜこのタイミングで問いを投げたのか」「生徒の表情をどう見ているのか」など、具体的に観察してメモを取りましょう。
観察後に担当の先生と話す時間をもらえると、さらに理解が深まります。
指導教諭からのフィードバック
授業の後には、担当の先生からフィードバックをもらう機会があります。
「声のトーンが良かった」「黒板の字が見やすかった」などの評価だけでなく、「ここはこう改善してみよう」といった建設的なアドバイスももらえます。
私は、フィードバックをノートに記録し、次の授業の目標を立てるようにしていました。
毎回の指摘が、確実に自分の力になっていきます。
自己評価の重要性
教育実習では、自分の授業を客観的に振り返ることがとても重要です。
授業後に「どこが良かったか」「もっと改善できることは何か」をノートに書き出し、次の授業に生かしていきましょう。
私は「今日の振り返りシート」を作り、簡単な図や感情も書き込むことで、前向きに成長を実感できるようにしていました。
教育実習の事後活動
実習の振り返りと反省
教育実習が終わったら、まずは自分の実習をしっかり振り返ることがとても大切です。
「どんな授業がうまくいったか」「困ったことは何だったか」「自分が成長できたと感じた瞬間はいつだったか」など、具体的に思い出しながら、今後につながる気づきを見つけていきましょう。
実習中は毎日が忙しく、気づかないうちにたくさんのことを学んでいます。 だからこそ、少し時間をとって静かに自分の実習を見つめ直すことが、次のステップに進むためにとても役立ちます。
私も、授業中に生徒が集中していないときがありました。 そのときの自分の対応を振り返り、次に同じような場面に出会ったとき、どうすればもっと良くできるかを考えることができました。 また、思った以上に生徒が楽しんでくれたアクティビティもあり、それは今後の参考になりました。
必要書類の提出と登録
教育実習が終わった後には、大学や実習校に提出しなければならない書類があります。
たとえば、以下のようなものがあります:
- 実習報告書
- 指導教員からの評価表
- 出席記録表
- 感染症チェックリスト(必要な場合)
- 実習記録日誌
これらの書類は、教員免許状を取得するためにとても大事なものです。 書類ごとに提出期限が決まっていることが多いため、スケジュール管理が必要になります。
私は提出日をカレンダーに書いて、見える場所に貼っておきました。 さらに、リマインダーアプリを使って通知を設定したことで、提出を忘れずにすみました。 実習が終わって安心しがちですが、書類の提出までが教育実習だと思ってしっかり取り組みましょう。
実習報告書の作成方法
実習報告書は、授業の記録や自分の学びをまとめるとても大事な書類です。
書き方に迷ったときは、大学から配布される記入例や先輩のアドバイスを参考にすると良いですよ。 一気に書こうとせず、日ごとに内容を整理しながら少しずつまとめていくと、丁寧に仕上げることができます。
以下のような表にして内容を整理すると、書くべきことが明確になります。
| 書く内容 | ポイント例 |
|---|---|
| 授業の記録 | 授業のテーマ、学年・対象、授業の成果 |
| 反省と考察 | うまくいった点、改善したい点 |
| 学びのまとめ | 自分の成長、次への課題、感じたこと |
私も、先輩の報告書を読んでから取りかかったら、内容の流れや表現の仕方がよくわかってスムーズに書けました。 また、自分の言葉で正直に書くことを心がけたことで、読み返したときに成長を実感できました。
教育実習を成功させるためのコツ
実施前の準備と心構え
教育実習は、事前の準備がとても大切です。
授業の進め方や板書の練習、教材作りなど、やるべきことはたくさんあります。 それに加えて、「どうすれば生徒が楽しく学べるか」「どんなふうに接したら信頼してもらえるか」といった気持ちの準備も必要です。
私は、実習前に友達とペアになって授業の流れを何度も練習しました。 お互いに授業をやってみせてアドバイスをし合ったことで、より現実的な準備ができました。 また、過去に実習した先輩から話を聞いたことも大きなヒントになりました。
先生との良好なコミュニケーション
実習中は、担当の先生や他の先生方との関係がとても重要になります。
毎日のあいさつや感謝の言葉を丁寧に伝えることで、良好な雰囲気を作ることができます。
また、授業準備や生徒対応などで悩んだときには、遠慮せずに質問してみることも大切です。 先生方は多くの経験を積んできているので、アドバイスもとても具体的で役に立ちます。
ある日、授業の進行がうまくいかずに落ち込んでいた私に、 指導教員の先生が「失敗も学びだから、自分を責めずに次の改善を考えて」と声をかけてくださいました。 その言葉に救われたのを今でも覚えています。
実習中に心がけるべきこと
実習期間中は、授業以外の時間も大切にすることがポイントです。
休み時間や掃除の時間、給食の時間なども、生徒とふれ合う貴重な場になります。
生徒との距離が近づくと、授業にも集中してくれやすくなります。 私は、昼休みに生徒と一緒にドッジボールをしたことで、ぐっと打ち解けることができました。
また、メモをこまめにとって、気づいたことを記録しておくと、後の振り返りにも役立ちます。 たとえば、「生徒が発言しやすかった場面」や「クラスの雰囲気がよかった時間帯」などを書いておくと、次の授業づくりにも活かせます。
教育実習に必要な資格と単位
教員免許状取得に向けた流れ
教員免許状を取るには、大学で決められた教育課程を履修し、単位をしっかり修得しなければなりません。 そのうえで、教育実習を受け、必要書類を提出することが条件になります。
以下のようなステップを踏みます:
| ステップ | 内容 |
| 1. 資格課程の履修 | 教育関連の授業を受けて単位を取得 |
| 2. 教育実習 | 指定された期間の実習を行う |
| 3. 書類提出・申請 | 実習報告書や評価表などを大学に提出 |
| 4. 教員免許申請 | 都道府県教育委員会に申請して免許を取得 |
ステップごとに確認しながら進めることで、ミスを防ぐことができます。
単位の修得について知っておくべきこと
教育実習を受けるためには、前もって必要な単位を修得しておく必要があります。
教育心理学、教育原理、教職実践演習など、教員としての基礎を学ぶ科目を落とさないようにしましょう。
たとえば、教育実習の履修条件として「○○の科目を合格していること」という条件がついている大学もあります。
私の友達は、必要な科目の履修を忘れてしまい、実習が1年延期になってしまいました。 そのときにとても落ち込んでいたので、事前にしっかり履修状況を確認しておくことが大切です。
教育課程と実習の関連性
大学で学ぶ教育課程と、実際の教育実習には深い関連性があります。
たとえば、「教育方法論」で学んだ指導案の立て方や、「生徒理解」の授業で学んだ発達段階の考え方は、 実際の教室で生徒と接する際にとても役立ちました。
授業中の言葉がけ一つをとっても、理論を知っているかどうかで対応が変わってきます。 実習前の学びが、現場での安心感につながります。
だからこそ、普段の授業や課題にも真剣に取り組むことが、実習成功のカギになるのです。
教育実習の体験談とおすすめ
先輩からの体験談
ある先輩は、「初日はとにかく緊張したけど、生徒が笑ってくれた瞬間に一気に緊張がほぐれた」と話してくれました。
また、別の先輩は、「失敗して落ち込んだこともあったけど、その度に先生や生徒に助けられた」と振り返っています。
実習は大変なこともありますが、その中で人とのつながりの温かさを感じることができるのも、教育実習の魅力の一つです。
オススメの教材とリソース
教育実習では、教材選びも重要なポイントです。
教科書だけでなく、ワークシート、カードゲーム、映像教材などを活用することで、 生徒が興味を持ちやすくなります。
おすすめのリソースには以下のようなものがあります:
- NHK for School(動画が豊富でわかりやすい)
- 小学生新聞や時事教材
- 教育系のSNSやYouTubeチャンネル
私が使ってよかったのは、「NHK for School」の科学の映像で、 実験内容を視覚的に伝えることができ、生徒の反応もとてもよかったです。
成功するためのヒント
教育実習を成功させるためには、次の3つのポイントが大切です。
- 準備をしっかりする(事前の計画が安心につながる)
- 生徒との関係を大切にする(信頼関係が授業の成功につながる)
- 先生に素直に相談する(迷ったら一人で抱えこまずに聞いてみる)
実習は大変な面もありますが、その分だけ得られる学びや喜びも大きいです。
私も実習を通して、「先生になりたい!」という気持ちがより一層強くなりました。 子どもたちとの出会いが、人生の宝物になる経験です。
まとめ
教育実習は、将来の教員としての一歩を踏み出す大切な経験です。
事前の準備、実習中の行動、事後の振り返りまで、一つひとつ丁寧に取り組むことで、 大きな成長を実感できるはずです。
最初は不安や緊張もあるかもしれません。 でも、それを乗り越えたとき、自分にとってかけがえのない経験となります。
「失敗しても大丈夫。次に活かせばいいんだよ」 その気持ちを忘れずに、一歩一歩進んでいきましょう。
教育実習を終えたあなたは、きっと一回り成長した自分に出会えるはずです。